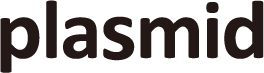「ダイアログ・イン・ザ・ダーク(DID)」をご存じでしょうか。視覚障害を持つ方に導かれて90分間、全くの暗闇の中で、いくつかのアトラクションを体験するものです(本当に真っ暗です)。
ダイアログ・イン・ザ・ダーク公式サイト
約4半世紀前、美大で2度目の学生生活を送っていた頃に話題になりましたが、当時は体験することはありませんでした。それが先日、所属する団体の主催で体験会があるというので、懐かしさもあって参加しました。詳細については、ぜひ体験していただきいのですが、個人的に考えるところがあったので記しておきます。
今回は所属団体とはいえ、私にとっては初対面の7名の方々とグループになり、それぞれに白杖を持ち、声を掛け合いながら、付かず離れず(実際には接触を繰り返し)、時には肩や腕を掴んだまま回ります。離れると怖いので、パーソナルスペースはものすごく小さくなり、常にお互いを気遣う必要があります。この「吊り橋効果」によって、物理的な距離だけでなく心理的な距離も一気に縮まるのです。
先日、トランプ大統領の就任によって、多くのアメリカ企業が多様性・公平性・包摂性(DEI)への取り組み撤回を表明しました。これ自体の良し悪しを語るつもりはありませんが、多様性の受容を社会で推進していこうという流れと、それに対する現場での無言の抵抗や軋轢は決してなくなることはないと考えています。それはなぜでしょうか。
私たちはそもそも未知の存在に対して、どちらかというと悪い状況を想像して、警戒するのが習性といえます。逆に同郷、同窓、同世代と聞くと、一気に警戒を解いてしまいます。これは島国ニッポン、村社会の我々に限らず、あるいは陸続きのヨーロッパなどの方が民族意識に基づく排他性は高いのではないかとも思います(憶測です)。
然るに心身に障害がある、外国人である、トランスジェンダーだと聞くと、そうした方々への理解がないと、警戒が先行してしまうのはやむを得ません。この警戒する人たち(私を含めて)を包摂性がないと批判するのもまた逆差別です。それが嫌な人には、嫌と言う権利があり、その権利もまた守られるべきです。敷衍すれば、職場で女性の登用が進まなかったり、給与が低かったりするのも、そもそもそこが(自称健常な)男性村だからなのかもしれません。
しかし、ではこうした状況を仕方ない、と諦めてしまっては、社会の分断はますます加速し、社会の潜在的可能性は閉じてしまいます。お互いに干渉しない、ある程度の棲み分けも必要でしょう。ただ、きっかけがあれば、意外と簡単に警戒を解くことができるのではないか。警戒が解ければ、新たな関係性を構築することができ、社会は拡張されます。今回のDIDへの参加でそんなことを考えさせられました。もちろん、職場のコミュニケーション改善などにもDIDは有効なツールになるでしょう。
ちょうど節分が終わったところです。私が考えるに、全国の鬼伝説の鬼は漂着した白人であり、各地での異形の存在に対する恐れが生み出したと考えています。角や虎のパンツはフィクションでしょうが、大きな体、怒らせて紅潮した赤い顔と肌、体毛の表現もそっくりです。白人は体温が高いので露出が多かったかもしれません。もしそうであれば、鬼退治は、古来からの人間の根源的な排他性を象徴しているのかもしれません(どっちが鬼やねん)。日本に限らず、世界に残る退治話も同様でしょう(これも憶測です)。